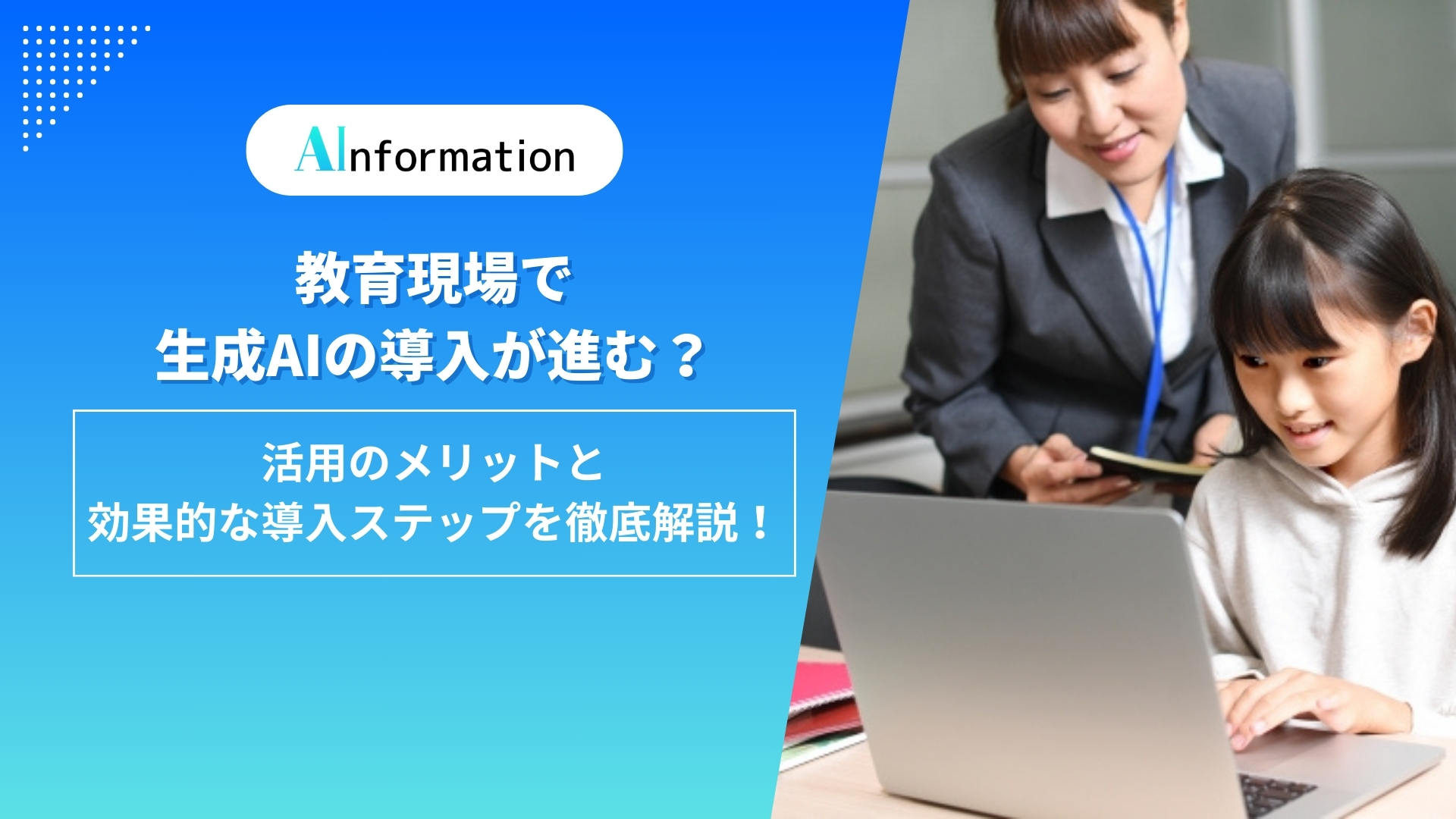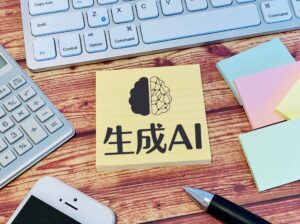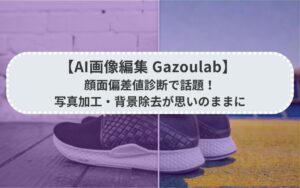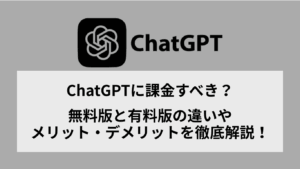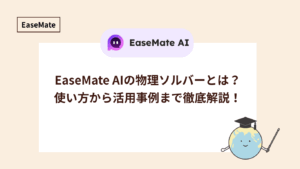今、ビジネス業界では「生成AI」の導入・活用が積極的に進んでいます。これにより作業の大幅な効率化が実現しているのですが、クリエイティブな分野の仕事でもサポートしてくれる強力なツールとなっています。そんな生成AIが教育業界でも注目を集めているのです。
そこでこの記事では、教育現場で導入が進もうとしている生成AIの実情や活用メリット、効果的な導入ステップについて解説していきます。
文部科学省が生成AIに対するガイドラインを策定!
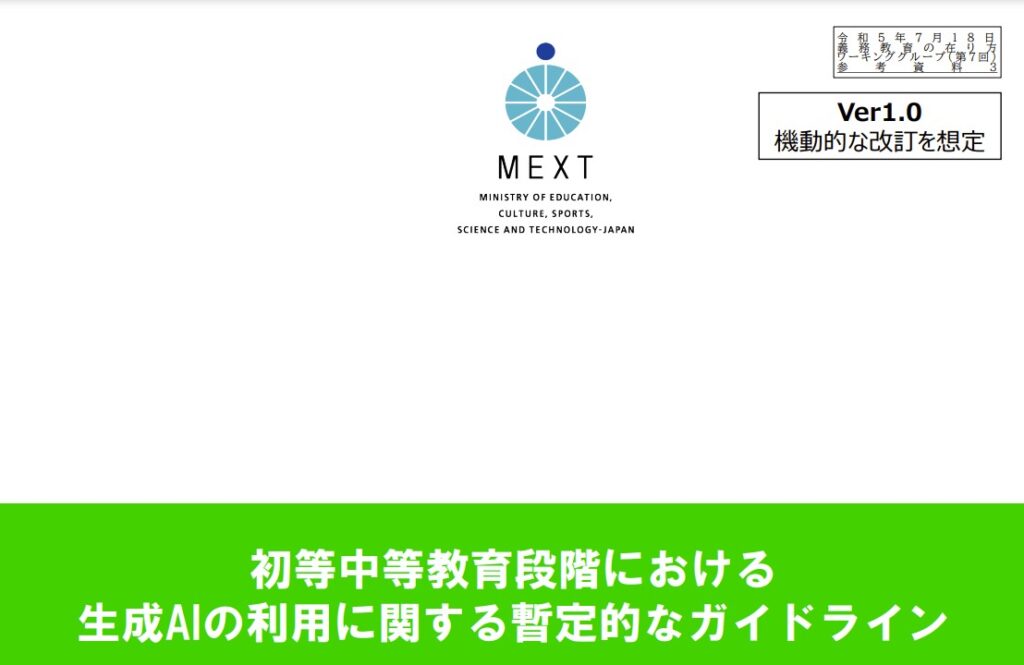
出典:https://www.mext.go.jp/a_menu/other/
ビジネス業界では活用が浸透してきた「生成AI」ですが、学校教育の世界においては少し縁遠い印象があるかもしれません。しかし、実は国(文部科学省)が、2023年(令和5年)7月にガイドラインを作成したのです。
策定した部署は、文科省・初等中等教育局。この部署は主に小・中学校の教育課程の基準を設定しているところ。ガイドラインを作った目的は、生成AIを教育現場で使うための指針を明確にするためです。また、高校や大学に向けての生成AIの利用についても指針が出ています。
そもそも生成AIとは何?
ところで生成AIとは一体どのようなものなのでしょうか?人が求める条件に対してその問いに対応した回答を導き出す技術で、「プロンプト」という条件を求める指示を生成AIに入力することで、新たなコンテンツを文字(テキスト)や動画像・音声形式のデータで排出することができます。
この生成AIは、自らが学習する「ディープランニング(深層学習)」という機能が搭載されていますが、この機能を活かして事前に必要な分野の情報をAI側に与えておき、何度もこの動作をリピートしていくことで、人が求める結果の精度を高めていくことができるのです。
文部科学省が作成した生成AIのガイドラインではどのようなことが書かれている?
文科省が作成したガイドラインの正式な名称は、「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」と「大学・高専における生成AIの教学面の取扱いについて」の2つ。
これらのガイドラインでは、どのような指針が出されているでしょうか?
ガイドラインの位置づけ
一般的にガイドラインというと、施策や計画の基本的な方向性や指針を示すものです。しかし、文部科学省が策定した生成AIのガイドラインには「暫定」という言葉が使われています。
このことから学校現場において教職員が教育の過程の中で、生成AIを完全なツールとして使うのではなく、現場現場ごとに適しているかどうかの参考として、取りまとめられたと考えられるのです。そのため必ずしも、学校で生成AIの活用を義務付けたものではないと解釈することができます。
ガイドラインが示す基本的な考え方
ガイドラインが示している基本的な考え方は、「生成AIの動きの仕組みを理解すること」や「教育の中での活用のあり方」、あるいは「生成AIを使う心構え」などが骨子になっているものの、生成AIがまだまた完全なツールではないため、「子供達の成長を十分に配慮しながら活用していく」としているのです。
教育現場で想定される生成AIの活用シーン
では、生成AIは教育現場でどのようなシーンで活用が想定されるのでしょうか?近年の教育では、大学などにおいて、「ラーニングコモンズ」という手法が取り入れられています。これは従来の講義のような教授から生徒に対する一方通行の授業ではなく、学生が主体となり、自主学習やグループ討議・学習を行うことで、協調性やコミュニケーション能力を高めていくことを目的にしているのです。
初等教育においてもこのような考え方に基づき、グループ討議で子供達のコミュニケーション能力も促進や想像力を養う仕組みが取り入れられていますが、生徒達だけでは気付かない発想を補うために生成AIが活用されようとしているのです。
生成AIを教育現場で活用するメリット
ビジネス業界では生成AIを駆使して新たな価値創造が実現できていますが、教育現場では生成AIはどのようなメリットをもたらすのでしょうか?具体的には、以下のようなメリットが考えられます。
- 生徒の個々の学力や関心に適した教材を創出
- 生徒の学習を適切なタイミングで指導
- 学習に対する意欲が高まっていく
- 学習の格差がなくなる
- データを活用することで教育の質の上げていく
- 教務負担の軽減
1.生徒の個々の学力や関心に適した教材を創出
子供達の価値観も大人と同じように多様化しています。その子供の個性や学力もまちまちですが、生成AIは、生徒たちの学力や関心のある分野に適した教育教材を生み出すことが可能になるでしょう。しかも、子供1人ひとりに合わせた学習のために、生成AIが個々の生徒の学力に合わせた学力向上がプランニングできる可能性も秘めています。
2.生徒の学習を適切なタイミングで指導
生成AIを活用することで、子供が学習している最中でも、適切なタイミングで指導することが可能になってきます。これまでの授業では、生徒達の個々学習の進捗具合を把握することは困難でした。しかし、生成AIの力を借りて、生徒1人ひとりの学習進捗をつかむことができるので、個別に不足している部分をサポートしたり、アドバイスすることができるのです。
3.学習に対する意欲が高まっていく
子供達の学習に対する意欲が低下していると、それを上げていくのは非常に困難です。しかし、生成AIは生徒1人ひとりに合わせた学習法を提示してくれるため、興味のある内容で学習することができます。
興味を示す教材で勉強したり、AIと双方向でやり取りをしながら学んでいくことで、やる気が起こり学習を楽しく感じられていくわけです。生徒も主体的に学ぶ姿勢を見せるようになり、学習意欲が高まっていきます。
4.学習の格差がなくなる
生成AIを活用すると、学習の格差がなくなってきます。義務教育では文科省から出ている教育指導要領のおかげで、全国均一的な教育を受けることができるはず。しかし、現実的には都市部と地方の学習格差が生じているのが実情です。昔からこの問題は教育業界の中では大きな課題となっていたのですが、生成AIを教育現場に取り入れることで、格差問題が解消されていくでしょう。子供達の質の高い教育コンテンツを提供して学ばさせることができるためです。
5.データを活用することで教育の質の上げていく
教育に関する諸々のデータを生成AIで分析していくことで、教育の質を上げていくことができます。教育関連のデータには、さまざまなものが含まれているのですが、個々の生徒の習熟度や全国模試の結果、あるいは科目毎にどのような傾向になっているのかを地域毎に実情を分析して把握することができるのです。
分析結果によって現状の教育計画に問題がないか、内容を修正していくことができるので、教育の質を高めていくことができます。これまで通り一辺倒な状況で教育プログラムの質をリアルタイムに見直す機会はありませんでしたが、生成AIがそれを実現させるのです。
6.教務負担の軽減
昔から教職員の負担が非常に大きいと言われてきました。通常の授業計画を立てるだけでなく、生徒達の出席状況や日常の生活状況、さらに部活動の指導まで指導するなど、教務の不安はビジネス業界の第一線で活躍しているビジネスマン以上かもしれません。
教職員に重くのしかかる教務を生成AIが軽減してくれるのです。自動化できる部分を生成AIに補完させることで、教務が軽減されて本来力を集中すべき点に教職員が意識を注ぐことができます。
教育現場に生成AIを取り入れるデメリット
教育現場に生成AIを取り込むことで、前述したようなメリットを見い出すことができるようになります。生徒達に効果的な学習機会を与えることができるので、生成AIに対する期待感が高まってきますね。
しかし、生成AI導入にデメリットがあることも認識しておかなければなりません。いわゆる「生成AIの活用が適切ではないケースを想定しておく」ということです。
具体的には、「生徒達の情報活用能力がまだ確立されていない状態で、生成AIを好きなように利用させたり、創造性を育成するシチュエーションで、すくに生成AIを使わせたりすることです。生徒自身で考える習慣をつけるためには、「生成AIありき」では機会に頼り過ぎて想像力・発想力を育てていくことはできません。
また、教職員側も生成AIのアウトプットだけを見て、子供達を評価していくことも、生成AI活用の活用法のデメリットとして国が警鐘を鳴らしているのです。
教育現場における生成AIの効果的な導入ステップ
ここからは教育現場において、どのようなステップで生成AIを導入していけばいいのかを説明していきます。具体的には以下のようなステップで進めていくといいでしょう。
- 第1段階:生成AIの活用方針の決定
- 第2段階:利用環境を構築する
- 第3段階:試験運用
- 最終段階:本格運用
第1段階:生成AIの活用方針の決定
まずは教育現場で生成AIをどのように活用していくのかを方針を決めることから始めます。生成AIは大きな可能性を秘めているので、生徒達の学習能力を子供の状況に合わせて高めていくことが可能です。
しかし、闇雲に生成AIを導入すればいいというものではありません。生成AIを生徒達の情報の取り扱いに対する理解度や教職員の状況に合わせて、どのようなシチュエーションで活用すればいいのか、活用の方針を検討して明確にしていくことが生成AI導入の第一歩になるのです。
第2段階:利用環境を構築する
生成AIの活用方針が決定したなら、次は具体的な利用環境を作り上げていきます。生成AIにも色々なツールがあるので、学校の教育方針に照らし合わせながら、ツールを選定していくのですが、安全かつ効率的に活用できるように、使い方のルール・マニュアル作成を含めながら、利用できる環境を構築していくのです。
企業であれば従業員に対していつでも安心して活用できる環境を作ればいいですが、教育現場においては、必要な時に生徒に使わせることができるようにしておくことが重要なポイントになってきます。
第3段階:試験運用
利用環境が構築できたなら、次には授業の内容に応じて、試験運用をしてみます。また試験的運用の段階なので、ここで運用環境やルール・マニュアルなどに改善点がないか1つひとつチェックしていくことが必要でしょう。
特に試験的な生成AIの活用で、子供達の学習進捗度がどのように推移していくかをチェックしていくことも、この段階での重要な項目です。
最終段階:本格運用
最終段階の生成AI本格的運用においては、運用のあり方に課題がないかを常にチェックするようにしなければなりません。定期的に教育に関するデータを生成AIに加えてアップデートしておくことを心がけておきましょう。そうしていくことで生徒達に対して適切なサポートをリアルタイムに行うことができるためです。
まとめ
教育現場においては、10数年前からICTの利活用が進んできました。学校でタブレットPCなどを使い教材コンテンツを子供達と共有しながらグループ学習を行といった授業展開で情報端末が用いられていたのです。
これもまた生徒の創造力を伸ばしていくことを目的にしていたのですが、生成AIの導入もまさにICT利活用の延長線上にあると言ってもいいでしょう。ただし、忘れてならないことは、先に述べたように生徒達の情報活用能力がまだ確立されていない状態で、生成AIを好きなように利用させてはならないことです。
このことを念頭に置いて、生成AIの活用を教育現場に取り込んでいくことで、子供達の可能性が限りなく広がっていくのだ思います。